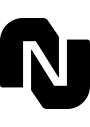Episode 3 もう一度、水の上へ。
共有
高校時代の木村亮太は、水球に専念した3年間を過ごした。だが、実はその中でも運命を変える瞬間が訪れていた。高校2年生の冬にU21カヌーポロ日本代表の公募選考会に自らエントリーしたのだ。
当時の木村は幕張総合高校の水球部員としての日常に没頭しており、カヌーポロの公式戦からはしばらく離れていた。だが、選考会に集まった即席チームで自分の力を試し、結果を残して代表入りを果たす。
「ほとんどぶっつけ本番みたいな形でした。でも、体には染みついているんですよね、カヌーポロの感覚が」
思いがけない代表入りは、再びカヌーポロと向き合うきっかけになった。水球で培ったフィジカルやスタミナは確実に役立ち、カヌーポロに戻ったときにプレーの幅を広げていた。高校卒業後の進路を考える時期に、この出来事は大きな意味を持つことになる。
そして木村は、埼玉県にある駿河台大学へと進学した。
ここでは専用コートが常設され、ナイター設備まで備わった環境で長時間の実戦練習が可能だった。
「大学では、もう一度カヌーポロで勝負しようと思っていました」
決して平坦な道ではなかった。家庭の事情もあり、学費や生活費の不安は大きかった。それでも祖母の支援に背中を押され、木村は駿河台大学で競技を続けることを決意する。
大学スポーツの中で、カヌーポロを明確に強化対象として位置づけ、専用コートや照明設備を備えて選手を継続的に育成する大学は、全国的に見てもごくわずかだった。駿河台大学はその数少ない拠点のひとつとして、全国から志のある選手が集まる場になっていた。
また、柔道やサッカー、駅伝のように複数の大学が競い合い、厚いピラミッドを形成する競技とは違い、カヌーポロは強化拠点が限られる。だからこそ、授業を終えた午後から夜にかけて一貫して練習ができる環境があることは、選手の競技力を底上げする大きな力となっていた。
入学して間もなく、木村は自分の立ち位置を思い知らされることになる。高校時代に「全国でも戦える」と感じていた自信が、ここでは簡単に崩れた。周囲には全国大会常連の経験者や、すでに代表歴を持つ選手まで揃っていたのだ。
「最初は本当に全然通用しなかったですね。自分の力なんてまだまだだと痛感しました」
その中で特に大きな存在だったのが、同期の柳選手だった。互いに強く意識し合い、切磋琢磨する関係だった。その競争が、自分をさらに成長させる原動力になった。

駿河台大学の練習は想像以上に厳しかった。艇を使った実戦練習に加え、徹底的なフィジカルトレーニング。午前に授業を受け、午後から夕方まで水上で汗を流す生活が続いた。練習の終盤には、腕や脚が動かなくなるほどの負荷があったという。だが、厳しい環境の中でも仲間たちがいたからこそ乗り越えられたという。
そして大学2年の夏、チームはついに大きな結果を掴む。日本選手権で初優勝。大学チームとしては前例のない快挙だった。
「高校の時に水球で負け続けた悔しさがあったから、勝てたときの喜びは大きかったです」
勝利は大きな自信になったが、それ以上に木村を成長させたのは「追われる立場」になったことだった。優勝した翌年からは、駿河台大学が挑戦者ではなく王者として見られるようになった。どのチームも「駿河台を倒せ」と挑んでくる。
勝ち続ける難しさとプレッシャーを、木村は身をもって体験することになった。その中で彼は、ただのプレーヤーからチームを引っ張る存在へと変わっていった。練習中に積極的に声を出すようになり、仲間をまとめる姿勢を見せた。中学時代にバレーボール部でキャプテンを務め、“勝てないチーム”をまとめてきた経験が、ここで活きていた。
「勝つチームも負けるチームも経験してきたからこそ、どうすればチームが一つになるかを考えられたんだと思います」
また、高校生活の終盤にU21代表に選ばれた経験は、大学期の木村にとって大きな軸になった。最後のU21年代で臨んだ世界大会では、得点ランキング1位(アジア人初/本人談)を獲得する。

「世界の大会で点を取れた。その感覚をつかめたのは大きかったです」
そう語った木村は、その後フル代表へとステップアップしていく。目的は“代表に入ること”から“世界で戦って活躍すること”へと明確に変わっていった。代表に選ばれることがゴールではなく、世界で結果を出すことが目的だと、はっきり意識するようになった。
フル代表として臨んだ最初の世界大会では、最終試合まで個人得点ランク1位を走った。だが、決勝局面でイタリアのストライカー・ルカ・ベリーニに抜かれ、首位を譲る。
「悔しさはありました。でも、世界は思い通りにいかないことの方が普通なんだと感じました」
カヌーポロの国際大会は、長年にわたりヨーロッパ勢が中心となってきた。イタリア、ドイツ、フランス、スペイン、イギリスなどは、クラブチームの層が厚く、ジュニアからシニアまで“プレーの場”が多い。リーグや大会の機会が豊富なため、実戦経験が積みやすい。
一方、日本は競技人口やトレーニング環境の面でどうしても不利になりやすい。だからこそ、U21でアジア人として得点王に立った事実は、競技の文脈の中でも意味が大きかった。単に個の得点力だけでなく、「少ない機会を最大化する技術選択と判断の精度」が評価されたと言える。だが、それでも木村が体験したフル代表での“最終盤での逆転”は、世界の厳しさをそのまま示していた。
「どれだけ点を取っても、チームが勝てなければ意味がない。点を取ることだけじゃなく、勝つために何をするかを考えるようになりました」
大学で掴んだ日本一、U21での得点王、そしてフル代表で味わった手応えと現実。結果と課題が同時に残る国際経験が、木村の競技観をさらに研ぎ澄ませていった。
大学卒業後、木村は地元に戻り、学童指導員として働きながら競技を続けている。母が関わる学童の職場は、代表合宿や海外遠征にも理解があり、実務と競技の両立を支えてくれる環境だった。クラブは地元の佐倉インヴァースに所属し、仕事と練習・遠征を行き来しながら代表活動を続けている。
「働きながら競技を続けられているのは、理解がある環境のおかげです」
日本の多くのマイナースポーツでは、競技活動と生活基盤の両立が恒常的な課題になる。遠征費や用具費の自己負担、合宿・代表活動に合わせた有給調整、トレーニング時間の確保など、選手側の工夫が不可欠だ。海外(特に欧州)と比べると、クラブ・リーグの広がりやスポンサー機会に差があり、年間を通した高強度の試合環境の有無は、経験値の面で影響が出やすい。
こうした背景は、木村にとっても例外ではなかった。環境の限界を実感する一方で、だからこそ日々の練習姿勢を見直す必要があった。日本国内で活動を続ける木村は、世界を経験してカヌーポロへの取り組み方を改めるようにもなったという。
「得意なことだけやってても世界では勝てない。苦手をつぶすのが一番の近道だと思うようになりました」
これまで避けてきた筋力トレーニングにも取り組み、体づくりに向き合うようになった。夜に走る、縄跳びを続けるといった地味なルーティンを“淡々と”積み重ね、競技に必要なベースを補強していく。

「自分一人の力じゃ続けられない。だからこそ、結果で返したい気持ちはいつもあります」
大学で形になった「選び続ける」姿勢は、社会に出てからも変わらない。選ぶたびに負担やリスクは伴うが、木村はその都度、自分の意思で“続ける”を選んできた。代表のユニフォームに袖を通すこと、地元クラブでの練習、学童で子どもたちと過ごす時間――そうした毎日の積み重ねが、自分を支えていた。
Episode 3 終わり
著者:山手 渉
カメラマン:高須 力