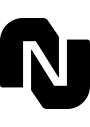Episode 2 水の中で見えた壁
共有
中学までに木村亮太は、勝てないバレーボールと、勝てるカヌーポロという二つの体験を積んでいた。その彼が高校進学を前に選んだ競技は「水球」だった。
よりカヌーポロを極めるために、水球で培えるボールコントロールや泳力が大きな武器になる――そう考えたからだ。両手でボールを扱うカヌーポロに対し、水球は片手での操作が基本。常に泳ぎながら瞬時にボールをさばく技術は、必ず自分の競技に還元できる。そう確信しての選択だった。
進学の選択肢として悩んだのは、地元にある君津高校、そして千葉県内で水球の名門として知られる幕張総合高校。どちらを選ぶかで、自分の未来が変わることは直感していた。
当時、日本の高校で水球部がある学校は多くはなかった。サッカーや野球のように全国に部活が存在するわけではなく、競技を続けるには“進学先の選択”が決定的な意味を持つ。幕張総合高校はその中でも突出した存在で、県内の有力選手が集まり、全国でも常に上位を狙う強豪校だった。
水球はオリンピック正式種目でありながら、日本国内では「知る人ぞ知る競技」といえよう。だが木村が高校進学を考えていた頃は、ちょうどインターハイの水球競技が千葉県で開催されることにもなっていた。事実千葉県内には水球部を設置する高校が複数あり、幕張総合や千葉敬愛、安房など県大会で優勝を争う実績校も存在している。強い環境に身を置けば、自分は確実に変われる――木村はそう直感していた。
そして決断する。
地元を離れ、毎日の長い通学を覚悟し、幕張総合高校への進学を選んだ。
「地元の高校に進めば、もっと気楽に過ごせたと思います。でも、それでは物足りない気がした。せっかくなら、もっと強い環境でやってみたいと思ったんです。」
こうして木村が選んだのは、「楽な道」ではなく「挑戦の道」だった。

新しい日々は、朝の電車から始まった。
まだ空が白んでいる時間に起き、6時過ぎの電車に乗る。片道2時間、往復で4時間。授業と練習を終えて帰宅すれば、夜はもう遅い。電車の中も貴重な睡眠時間だったという。
「大変だと思うより、“そういうものだ”って割り切ってました。自分で選んだ道だから当然だって」
部活を終えて友達と寄り道する時間も、木村には十分になかった。
練習後はただ駅に向かい、また2時間の電車に揺られるだけ。高校生活というより、日々が競技生活そのものになっていた。
ただ、その厳しさを補ってくれる環境もあった。幕張総合には大学のような選択授業制度があり、午前を休みにして午後から練習に集中することも可能だった。通学の負担は大きかったが、その分「競技にすべてを捧げる」日常に身を置くことができた。
水球は“水中の格闘技”と呼ばれる。常に泳ぎ続け、足を着けることは許されない。相手とぶつかり合い、腕をつかまれ、沈められることもある。水面上で見える以上に、水中では熾烈な駆け引きが繰り広げられていた。水の中だから反則を判定しづらく、時にラフプレーぎりぎりの攻防になる。そこでは体格、筋力、持久力、そして水中での知恵がすべて試される。
「最初の頃は本当にきつかったですね。冬の練習は冷たい水に入って2時間で10キロ泳ぐメニューが普通にあった。最後は腕も足も動かなくなって、もうダメだと思うこともありました」
当時チームを指導していたのは外国人コーチだった。国際基準の練習は量も負荷もこれまでとは比べものにならず、徹底した泳ぎ込みが続いた。水から上がると腕も脚も動かなくなるほどの負荷だったという。
しかし、続けるうちに体は順応していった。冷たい水の抵抗に慣れ、心肺機能が強化され、持久力も格段に上がっていったのだろう。練習が厳しければ厳しいほど、終えたあとの充実感は大きく、木村は「自分が強くなっている」という手応えを確かに感じるようになった。
さらに意外な発見もあった。
「カヌーポロで身につけたシュートの感覚が、水球でもそのまま活きたんです」
水球部の仲間からは「その投げ方はカヌーポロの動きだね」と驚かれることもあった。逆にカヌーポロに戻ったときには「その動きは水球っぽい」と言われる。両方の競技が互いに影響し合い、自分だけのスタイルを作り上げていく感覚があった。
ボールをリリースする角度、タイミング、相手の視線をずらす工夫――。
艇の上で培った技術と、水中での駆け引きがシンクロし、木村のプレーにまた新しい強さが身についていった。
水球という競技は、日本ではまだマイナーな存在だ。サッカーや野球のように観客が押し寄せることはなく、競技人口も限られている。だが、その分「続ける者だけが知る世界」が広がっている。練習の過酷さも、試合での激しさも、やった者にしか分からない達成感を生む。木村にとっては、それが大きな魅力でもあった。
「水球で鍛えられた泳力や体力は、後のカヌーポロに間違いなくつながった」
水中での格闘をくぐり抜ける日々。その厳しさは確かに過酷だったが、木村のアスリートとしての芯をさらに強固にしていった。
入学からわずか3か月。木村は総体で早くも大きな舞台に立つことになった。相手は、県内でも強豪として知られる君津高校。3年生の県選抜選手を相手に互角以上に渡り合えたことは、本人にとっても大きな手応えになったという。
「自分でも驚きましたね。環境が変わるだけで、こんなに伸びるんだって。強い仲間と練習すること、全国を意識しているコーチに指導されること、それだけで一気に成長できたんです」
その後は木村自身も千葉県の選抜メンバーに選ばれ、全国大会に出場。ベスト8まで勝ち上がる経験を得た。全国の舞台は想像以上に広く、強豪校の選手たちは一人ひとりが完成されたアスリートのように映ったのだろう。
だが、そこで同時に直面したのが「フィジカルの壁」だった。水球は体格差が勝敗を大きく分ける競技だ。リーチの長さ、肩幅の広さ、筋肉量――そうした身体的条件がそのまま優位性につながる。木村は早稲田大学などの強豪と合同練習をした際、その差を痛感する。
「どんなに動いても、相手に体を当てられたら一歩も動けなくなる。シュートに持ち込めるはずの場面で、腕一本で止められてしまう。悔しかったけど、“これが現実か”と思いました」
小学生の頃からカヌーポロで全国優勝を経験し、「勝てる競技」で自信を培ってきた木村にとって、この壁は大きな葛藤だったのだろう。結果を出せる世界と、結果を出せない世界。その二つの現実を同時に突きつけられる中で、彼は水球を投げ出さなかった。
「カヌーポロだったら勝てるのに、って思う瞬間は正直ありました。でも同時に、水球に挑戦しているからこそ、自分に足りないものが見えた。だから続けられたんだと思います」
水球は、日本では競技人口が少なく、世界的に見れば不利な条件が多い。欧州やアメリカのフィジカルに優れた選手たちと比べれば、体格や環境の差は明らかだった。けれど、その限られた環境の中で必死に戦うことにこそ、価値があった。木村が直面した「壁」は、日本の水球界全体が抱える課題でもあったのだろう。
全国ベスト8という結果は誇らしい一方で、同時に木村へ課題を突きつけるものだった。だがそこから逃げなかった。壁にぶつかりながらも、泳ぎ込みで体力を補い、技術でカバーしようと必死に取り組んだ。
「勝てないから意味がないんじゃなくて、勝てないからこそ得られるものがある。そう思えたのは、バレーボールで負け続けた経験があったからかもしれません」
この経験は決して輝かしい頂点ではなかったが、木村にとっては「次の挑戦への布石」だった。勝つことの喜びも、負けることの悔しさも、両方を抱え込んだまま進む道。その姿は、「後悔しない選択」の体現そのものだった。

そして幕張総合高校での3年間を振り返るとき、木村は必ず「家族」の存在を口にする。
「定期代や遠征費、道具代……本当にお金がかかりました。自分では稼げないから、全部親が負担してくれていた。申し訳なさはずっとありました」
大きな通学の負担も含め、家族にとってもその支えは決して小さなものではなかったはずだ。だが、木村はその後も挑戦を続けることができた。日常のひとつひとつが、自分を後押ししてくれていたからだ。
「当時は“ありがとう”より“ごめん”の気持ちの方が強かったですね。でも両親が応援してくれて、試合で活躍を見せられたときは、やっぱり嬉しかったです」
高校生活を終えて振り返ったとき、木村の心にあったのは「後悔のなさ」だった。
「君津の高校に行っていたら、もっと楽だったかもしれない。でも、自分はあえて幕張総合高校を選んだからこそ、成長できた。だから一切後悔はないです」
水球で全国優勝することは叶わなかった。体格の壁に阻まれ、結果だけを見れば決して華やかなものではない。だが、その厳しい環境に飛び込み、自分の限界に挑んだ経験は、後のカヌーポロ人生に欠かせない土台となった。
木村は「後悔しない選択」として幕張総合高校を選び、そして高校卒業後、再び大学生活でカヌーポロの世界に戻ることとなる。そこで彼を待っていたのは、日本一、そして代表への道だった。

水球で味わった過酷さ、壁にぶつかりながらも乗り越えてきた3年間は、次なるステージへの大きな力へと変わっていく。
Episode 2 終
著者:山手 渉
カメラマン:高須 力