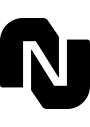Episode 1 すべては水の上から始まった
共有
静かな水面を、切り裂くように艇が滑る。
ぶつかり合う船体、飛び交うボール、交錯する視線。
激しさと緻密さが絡み合う、奇妙なスポーツがある――それが、カヌーポロだ。
体格で勝る相手に真正面からぶつかっても、倒されてしまうだけ。
けれどこの競技には、“逆転の余地”がある。艇の角度、視野の取り方、シュートフォーム、わずかな判断の違いが勝敗を分ける。ただ速く、強いだけじゃない。頭と身体を同時に使いこなす、そんなゲームだ。
世の中の人は、この競技を知らない人も多いだろう。
観客で埋め尽くされるスタジアムも、ヒーローインタビューもない。
それでも、そこに人生を懸ける者がいる。
「僕は、他の道をあまり考えたことがないんです」
そう語る木村亮太の声には、静かだが揺るがない芯があった。
25年にわたり水の上で積み重ねてきた時間が、その言葉を支えている。

思えば、その始まりも偶然だった。
木村は千葉県八千代市に生まれた。海好きの父親、そして母親は県大会で優勝経験を持つ競泳選手で、家族全員が水とともに生きてきた家庭環境だった。兄二人も当然のようにプールに通い、幼い頃から水泳は日常の一部になっていた。
6歳のとき、父の転勤で千葉県君津市へ引っ越す。新しい生活の中で、地元のスイミングクラブに入会した。そこでは室内プールのコースロープを外し、カヌーポロの練習にも活用していた。プールで泳ぐだけでなくカヌーまでできる施設は近隣では非常に珍しく、木村にとっては思いがけない貴重な環境との出会いだった。
「最初は、兄がやってたから。自分も自然に始めたって感じでした。」

特別なきっかけではなかった。ただ兄の後を追っただけだった。
兄の背中を追いかけて、なんとなく乗ったカヌー。それが、人生を動かす出会いになるとは、この時まだ知らない。けれどその“なんとなく”こそが、誰よりも深く彼の人生を決定づけていた。無意識の選択が、やがて明確な「意志」に変わっていく。
水の上に浮かび、パドルを漕ぐとスッと艇が進んでいく。水面を滑るような感覚と、心地よい揺らぎ。水泳とは違う、“水と遊ぶもうひとつの感覚”に、彼は一瞬で引き込まれた。先先に競技を始めていた兄の遠征にも同行し、大会の熱気や勝負の空気を肌で感じる。7歳の少年にとって、それは日常からかけ離れた世界だった。気づけば、他の選択肢はなかった。
木村の成長を支えたのは、偶然の出会いだけではない。
当時の君津のスイミングクラブには、室内プールのコースロープを外し、カヌーポロの練習ができる環境があった。カヌーポロは水上で行う球技だ。通常は屋外で練習するため、冬場は極端に活動が制限される。だが、木村は幼少期から一年を通して練習を重ねることができた。また、そのクラブにはカヌーポロ日本代表経験のあるコーチも在籍していたことも、大きかった。
最高のコーチ、最高の練習場所、この君津という場所には、彼の上達を自然に加速させる環境が整っていたのだった。
「カヌーポロってカヌーのいろんな要素があるスポーツなんです。たくさんの技術を身につけられるので、楽しさをいつも持っていました。」
スプリントのようにスピードを競う種目。
スラロームのように障害物を回避する種目。
小学生のうちから多彩な競技に触れることで、技術の幅が広がり、探究心が刺激され続けた。
やがて木村は全国大会への出場も果たす。参加選手はわずか50〜100人程度。チーム数でいえば10にも満たない規模だったが、それでも“全国”を本気で目指す経験は、彼の内面に火をつけた。
「この競技だったら、自分もトップを目指せるかもしれない」
そう思えたのは、単に勝てたからではない。小さなパドルと、両手で扱うボールの間に、自分だけの工夫やひらめきを持ち込める余白があった。自分なりの戦い方が見つかる競技だった。
艇を自由に動かす技術、パスやシュートの精度、そして試合中の判断力。カヌーポロは、体力とテクニック、戦略を総動員する“複合型スポーツ”だった。
勝った時には「なぜ勝てたのか」。負けた時には「どこに原因があるのか」。小学生の頃から常に自分に問いかけ、答えを探そうとしていた。その習慣は、やがて彼を「考えるアスリート」へと導いていく。
小さな艇の上で、自分がどこまで行けるのか。
その問いを胸に、心の奥に芽生え始めていた。

小学校時代はカヌーポロに打ち込んできた木村だったが、地元の中学に進学すると、もう一つの競技と出会う。背中を追い続けてきた二人の兄がカヌーポロ活動と並行して打ち込んでいた、バレーボールだった。
実は当時の木村が地元のスイミングクラブでコースを使ったカヌーポロの練習ができるのは、クラブの営業が終わった後の夜や土日だけだった。限られた時間しかできなかったからこそ、部活動と両立できる環境が成立していた。
中学校でバレーボール部に入部。ところが同期の部員は自分のみ、つまりたった一人だったこともあり、年次が上がった時には自然とキャプテンを任されたという。
だが、現実は厳しかった。毎試合のように敗戦を喫し、卒業するまでに目立った成績を残せなかった。
勝てない悔しさ、ひとりで部を背負う責任。結果だけを見れば「敗北」の3年間だった。
「当時は、たぶんそこまで強く『勝ちたい』という気持ちではなかったのかもしれません。でも3年が終わった時に、『一人でもやり切ったな』という達成感はありました。」
中学生活最後の試合後には、自然と涙がこぼれたという。
勝てなかったとしても、続ける意味を知った時間だった。幼稚園時代、マラソン大会で最後尾をスキップしながらゴールしていた“マイペースな少年”にとって、「誰かのために」続ける経験は新鮮だったのだろう。
「まさか今、自分が日本代表のキャプテンになってるなんて、あの頃は全く想像してなかったですね。」
一方で、技術的な面では思わぬ相乗効果もあった。バレーボールの練習をする中でカヌーポロにシンクロするような動作、応用できる技術もあったという。
「カヌーでボールを投げるリリースの動作とバレーのアタックの動作部分って多分近しいものがあると思います。今思い返すと、その時期があったから意識してできるようになったのかな。」
異なる競技で得た感覚が、カヌーポロに還元されていく。無駄な経験など、一つもなかった。
異なる競技で得た感覚が、カヌーポロに還元されていく。そして中学3年時、カヌーポロの全国大会で優勝を果たす。“負けたバレー”と“勝てたカヌーポロ”。その両方を経て、彼の内側ではすでにカヌーポロが揺るぎない核になっていた。
「たぶん、自分は“なんで?”って考えるのが好きなんです。勝てたら、なぜ勝てたか。負けたら、どこに原因があったのか。常に分析してる感じですね」
問いを立て、自ら答えを探す。その思考の習慣が、彼を“強く、賢く”していった。。
そして、もう一つの大きな支えは“競技の温度感”だった。まだ知る人の少なかったカヌーポロには、競い合いながらも互いを認め合う独特の空気があった。仲間の成長を自分のことのように喜ぶ世界。その中で、木村はゆっくりと、しかし確かに、アスリートとしての輪郭を形づくっていった。
“負けたバレー”と“勝てたカヌーポロ”。そのどちらにも確かな意味があった。
勝てない時間も、勝てた瞬間も、どちらも自分を支える要素になっていた。
勝利も敗北も、どちらも確かな糧になった。“選び続ける”ことが、自分の物語の唯一の答えだった。
兄たちの背中から始まったその道を、自分の足でまっすぐに歩き続ける。
水の上には、いつも“自分だけの場所”があった。
けれど、このあと彼は一度その場所を離れることになる。
それはもっと強くなるための選択だった――水球という、もうひとつの水上競技へ。
Episode 1 終
著者:山手 渉
カメラマン:高須 力